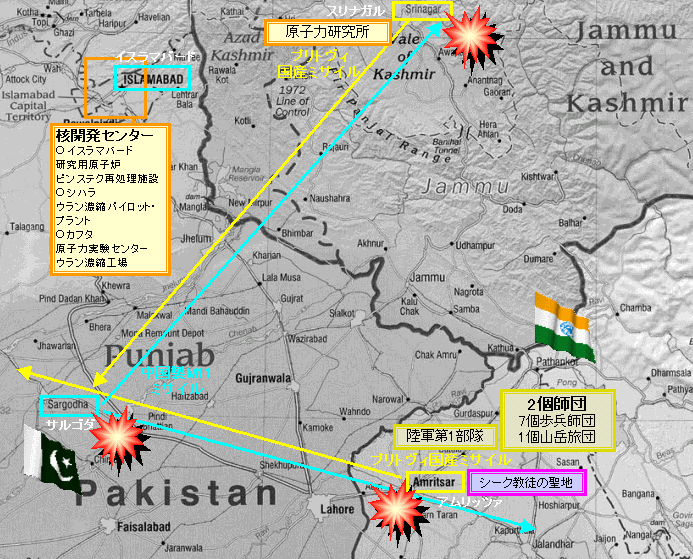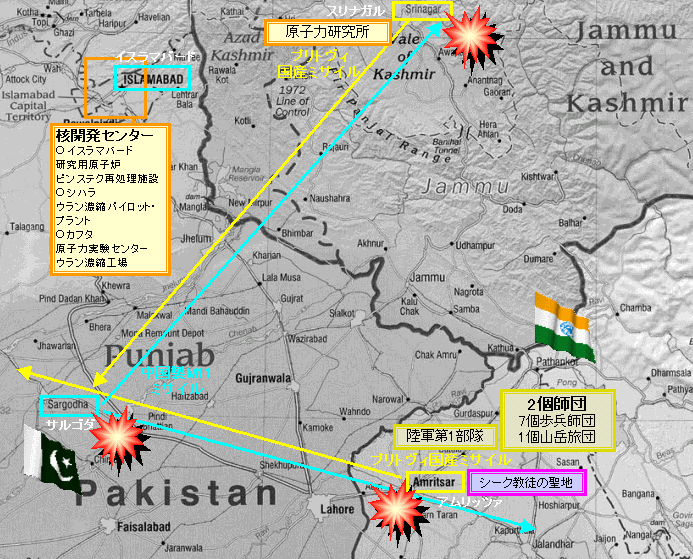
|
|
|
★「ALWAYS 三丁目の夕日」…人情たっぷりの「昭和」
東京タワーの完成、長嶋茂雄の巨人軍入団(いずれも昭和33年)など、夢と希望にあふれていた昭和30年代。郷愁を誘う“よき時代”に暮らした庶民を人間味たっぷりに描いた映画「ALWAYS 三丁目の夕日」が、11月5日から全国東宝系で公開される。
当時の商品パッケージが復刻されたり、30年代をテーマにした施設などに人気が集まるなど昭和ブームが続いている中での上映だ。
原作は西岸良平さんの漫画「三丁目の夕日」。コミック本はこれまでに約1400万部が販売されている。映画では、吉岡秀隆、小雪、堤真一、薬師丸ひろ子、三浦友和らが「夕日町」に暮らす住人を個性豊かに演じる。家庭に入り始めたテレビ、洗濯機、冷蔵庫の「三種の神器」や、近所の家に押しかけて見たプロレス中継など、当時の光景も見事によみがえる。
厳しくて頑固な父、いつも優しくかばってくれた母、あるいはわんぱくで手を焼いた息子、泣き虫だった娘……と、見る人一人一人の思い出に語りかけてくる作品だ。悲しい涙ではなく、ジーンと心が熱くなって流れる後味の良い涙。人との温かい触れ合いがあったあのころの、今は心の奥にしまってある「思い出」の宝箱をちょっと開けてみたくなる。
(2005年10月31日 読売新聞)

 見どころ 見どころ
1400万の発行部数を誇る、西岸良平の傑作コミックを映画化。VFXを駆使して再現された昭和30年代の東京下町を舞台に、人々の人情味あふれる物語が展開する。
ストーリー
個性豊かな住人が暮らす、昭和33年の東京・夕日町三丁目。そこにある鈴木オートに青森から上京した六子が就職。大企業を期待していた彼女は、鈴木オートが自動車修理工場だと知り落胆してしまう。
○前々から「貧しかったけど逞しい、あの頃のことを3DCGで再現できないか?」と模索してきた私だが、この映画によって実現した感がある。上の映像を見ていると、私の両親の顔がダブってくる。ここ「日々雑感」でも、こうした試みをしていきたい。
▲「ALWAYS 三丁目の夕日」監督 山崎 貴
昭和33年(1958年)の東京・下町を舞台に、人々の暮らしと人情を描く「ALWAYS 三丁目の夕日」が来月5日、公開される。
CGを多用したSF映画で知られる山崎貴(やまざきたかし)監督(41)の意欲作だ。(原田康久)
◎
「ハリウッドにも負けない」と評価の高いVFX(視覚効果)技術を駆使し、「ジュブナイル」「リターナー」とSFの話題作を撮り続けてきた。その技術をそっくり、昭和の再現に使った。
「どこにもない風景を作るSFと違い、多くの人々の記憶に残る時代を描くのは怖かった」
だが、スタジオに建てられたセットと、CGを合体させて作った映像はまさに圧巻。「昭和30年代に時間移動して、そのまま収録してきたというレベルの映像を目指した」の言葉がうなずける技術力だ。
だが、今回は「CGと分かられてはいけない仕事」とも心得ていた。主役は当時を生きた人たちで、彼らの織りなすドラマが中心となるからだ。
終戦から13年――。がれきの下から再出発した国民の希望を象徴するように、建設中の東京タワーが日に日に高さを増している。その空の下で、自動車修理工場を営む鈴木家(堤真一、薬師丸ひろ子、小清水一揮)、売れない小説家(吉岡秀隆)ら、市井の人々の暮らしが描かれる。テレビや冷蔵庫が家に来て、新製品のコーラを不気味に感じたあのころ。「『そんなこともあったね』と思い出せる話にしたかった」と話す。
▲アニメーションと実写 垣根消える?
アニメーションの技術を駆使した実写映画や、実写映画でよく使われる手法で作られたアニメーション映画が、次々と公開されている。アニメーションと実写の垣根はやがてなくなるのか。また、世界に誇る日本のアニメーション技術は、実写映画の新たな地平を切り開くのか。現状を取材した。
佐藤江梨子主演の「キューティーハニー」は、アニメーションの技術が生かされた実写作品
ピンクのコスチュームに身を包んだセクシーな戦士が、空中を乱舞しながら、敵の攻撃をかわしていく。見たことのない新鮮で迫力ある映像が、スクリーンいっぱいに広がった――。
永井豪の漫画を映画化した「キューティーハニー」の一場面だ。
内容もさることながら、役者が演じるこの実写映画には、アニメーションの技術がふんだんに生かされている。冒頭の映像は、通常の映画なら役者をワイヤでつるして撮影したり、役者をコンピューター・グラフィックス(CG)で描き直したりするところだろう。
しかし、庵野秀明監督は「ワイヤアクションには新味がない。CGは人間の表情をうまく出せない。生身の人間が汗をかいている感じや、歯を食いしばっている表情をどうしても出したかった」と語る。
そこで、「新世紀エヴァンゲリオン」など数多くのアニメーション作品を手掛けてきた庵野監督は、アニメーションの技術を応用。「ハニメーション」と名付けた技術で、迫力ある戦闘場面を作った。
まず、通常のアニメーション作品のように、アニメーターがハニーの連続した動きを描いた原画を作成。次にハニー役の佐藤が、絵の通りにポーズをつけて、ひとコマずつ撮影する。1秒間の映像用に12コマ分の撮影を行った。
これにより、アニメーションのキャラクターのように、ハニーは自由に動くことができた。庵野監督も「大変な撮影なので短いシーンとなったが、それでも際立って新鮮な映像に仕上がった」と満足そうだ。
「今後は日本の優秀なアニメーターにも加わってもらい、彼らの感性を導入して、従来のCGにもアニメーションにもない新しい表現を生み出したい」と、三宅社長。また、庵野監督は「道具が違うだけで、最初から僕自身の中に両者の垣根はない」と言い切る。
少なくとも、日本のアニメーション業界にひしめく多くの才能が、新しい表現を切り開きつつあることは確かなようだ。
★映画「ゴッド・ディーバ」エンキ・ビラル監督に聞く
 映画「ティコ・ムーン」で臓器移植やクローンを描いて見せたように、異世界を描きながらも、いつも現実の世界を直視した問題を提起する。 映画「ティコ・ムーン」で臓器移植やクローンを描いて見せたように、異世界を描きながらも、いつも現実の世界を直視した問題を提起する。
「人間性の喪失を問題にしたかった。限りなく進む遺伝子工学と、それを商売として扱う巨大企業がある。これらの企業の肥大化によって、いつか人間性が踏みにじられることはないだろうか、と」
「人間性の喪失」――。それは図らずも、公開中の押井守監督作品「イノセンス」と同じテーマだ。
「つまり、アーティストは、政治家たちの危機感よりはるかに研ぎ澄まされた感性で、問題に気づきだしたということだ。今こそ、アーティストの提起する問題を論議すべき時だ。そして僕らは、作品を通じて人々の感性に訴えるだけでなく、何か行動を起こすべき時かも知れない」
|
|
|