昨日← 05/02/15 (火) →翌日

0−10℃
【トピック】 ★ロシアの今年の大規模資源開発入札、外資参加認めず
【モスクワ=五十嵐弘一】インターファクス通信によると、ロシアのユーリー・トルトネフ天然資源相は10日、極東・サハリン沖の石油・天然ガスを開発する「サハリン3」プロジェクトなど、今年予定される、大規模な天然資源開発の入札に、外国企業の参加を認めないと語った。
当地の外交筋によると、石油パイプライン「太平洋ルート」に原油を供給する東シベリア油田の入札で、日本企業が参加できない恐れも出てきた。
新たな政府方針によると、入札への参加は、少なくとも51%以上の株式を露資本が所有している企業に限られる。これにより、「サハリン3」(エクソンモービルが開発参入を企図)のほか、バレンツ海油田、露最大の未開発金鉱床「スホイ・ログ」、東シベリアのウドガン銅山など、大規模な開発案件への外国企業の直接参加が不可能となる。
プーチン政権がこれほど明確な外資排除を打ち出したのは初めて。外交筋は、ロシアが加盟を目指す世界貿易機関(WTO)の「精神に反することは明らかだ」と言う。新方針が施行されれば、外国企業の対露投資意欲を落ち込ませることになりそうだ。
(読売新聞)
★サハリン2で巨額の損失=三井・三菱などに補償要求−ロ会計監査院
【モスクワ9日時事】9日付のロシア紙ベドモスチは、同国会計監査院が極東サハリン沖の石油天然ガス開発事業「サハリン2」で、ロシア側が総額25億ドル(約2600億円)相当の巨額の損害を受けたとし、開発業者に補償を要求していると報じた。
同事業は英・オランダ系メジャー(国際石油資本)のロイヤル・ダッチ・シェル、三菱商事、三井物産の3社が推進。外資によるロシア最大級のプロジェクト。
★北東アジアにおけるロシアのエネルギー開発プロジェクト
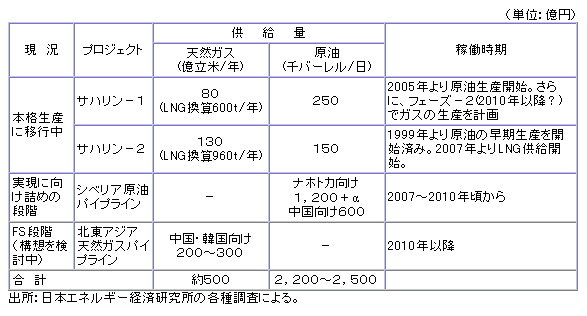
★ ロシアの経済成長---2004/5/28 田中直毅
プーチン大統領は年次教書演説で石油パイプラインのことを口にしました。バレンツ海を通じてヨーロッパに引くものがあります。それからシベリアを通って太平洋岸、ナホトカにまでパイプラインを引くという構想があるのですが、これについて、もはや決定は遅れすぎている、どういうやり方でいくらぐらいかかるものをいつまでの時点でどこと組んで造るのか、もう決める時期にきているという発表をしたわけです。
現在の世界の中で昨年はロシアの石油生産量がサウジアラビアを上回りました。そういう意味では世界一の原油生産国ということになります。ただロシアの場合は井戸元が大陸の中にあるものですから、これを輸出品として外に出すためにはどうしてもパイプラインが要る。パイプラインの不足のために石油は井戸元では生産されるのだけれども、円滑には輸出できない。そういう意味では輸送経路にかかわるネックが生じているというのが現状です。そして現在のように石油の価格が大幅に上がっているわけですから、ロシアにとりますとこれはもうパイプラインはできるだけ早く造って、そしてロシアの経済建設のために役立てたい、と思うのは当然のことでしょう。プーチン大統領のもとにおいて、権威主義的な経済システムというものが動き始めていますので、果たしてロシアの経済体質はどうなるのかというテーマがあります。
このプーチン大統領が上下両院の議員を集めたところで年次教書演説をやって、しばらくしてモスクワの地方裁判所がロシアの最大の石油企業であるユーコスに対して、税金を免れていたというので追徴の措置を是認しました。990億ルーブルと言いますから日本円にしておよそ、4000億まではいかないようですが、3000数百億円に相当する税金をユーコスに払えということを、モスクワ地裁が是認しました。ユーコスのスポークスマンによると上告するということのようですから、税金の支払いはその後になるのだろうと思いますが、今のロシアの体制からいくと、次の裁判所でもおそらく税金支払命令が是認されるということになるわけです。このためユーコスの株価はこの判決が出て大幅に下がったということのようです。
そういう意味ではロシアの経済体質をどのように考えるのかということについては、西側でもいろいろな意見があるわけですが、原油価格、あるいは非鉄金属をはじめとした天然資源価格の上昇を受けて、ロシアの経済に大きなうねりがきている、ということについては国際的な合意があることは明らかです。ロシアを21世紀の国際システムの中でどのように位置付けるのかについては、いろいろな意見があります。ブレジンスキーというアメリカの国際政治学者で昔は安全保障担当の大統領補佐官もやった人なのですけれども、彼は21世紀の国際社会を6つの単位でその相互関係を織りなすものとして見ているわけですが、その中にロシアが入っています。従来言われた三極では、米国、EU、日本が入っているわけですが、その他に中国とインドが入る、これは世界の中で相当合意ができている話なのだろうと思うのですが、そこにロシアも入れているというのがブレジンスキーの一つの見識と言いますか、ある種のものの見方を示しているのではないかと思います。
(中略)
どうやらプーチン大統領はこの東シベリアから大慶にまで石油パイプラインを引っぱってくる構想に賛成ではないようであります。そしてバイカル湖を大きく北の方に迂回しながら、ナホトカまで持ってきて、ナホトカまで持ってくればこれは日本のみならずアメリカに対してもあるいは中国の沿岸部に対してもあるいは韓国に対しても、この油が売れるわけですから、買い手独占ということは避けられるわけです。もし大慶まで持ってくるということになりますと、大慶は海からずいぶん内陸に入ったところですから、買い手は中国しかいないというのが現状なわけで、そうした力関係には入りたくない。石油の値段についての決定権、あるいはどこに売るのかということも含めてこれはロシアの側で維持しておきたいというのがプーチン大統領の基本的な考え方でしょう。
(中略)
現在シベリアで開発されています石油は、もしそれが全額全量中国が引き取れるということになりますと、中国の輸入量のうち現在の輸入量の3分の1はまかなうことができる。もちろん中国の石油消費は増えていますので、それだけではずっと3分の1まかなえるわけではないのですが、現状を考えれば3分の1程度はまかなえるほどそれほど多いわけです。逆に言いますと、日本が中東に対する石油依存度を下げようと思えば、ナホトカまできた石油を買うということはそれなりに石油の輸入先の多角化には成功するということでもありますので、日本も無関心ではいられない、こういうテーマです。
【私的めもらんだむ】
秘本兵法28計「上屋抽梯」
「これを仮(いつわ)るに便をもってし、これを唆(そそのか)して前(すす)ましめ、その援応を断ち、これを死地に陥(おと)す。毒に遇うとは、位当たらざればなり。
唆かすとは、利もてこれを使うなり。利もてこれを使えども、為すの便を先にせざれば、なおかつ行なわざることあらん。故に梯を出すの局、まず梯を置くべし。或いはこれを示すに梯をもってす」
相手を利益で誘導そそのかし、何ら手だてを講じることなく、立ち往生させる。これみよがしに梯子をかけて、相手が利益につられて登り渡ったところで梯子を外す。そして「上屋抽梯」のもう一つの目的「自分だけよい所に赴き、後の者を来させない」で決着をつける。日ソ不可侵条約が破られた時のように、まさしく策謀実務派プーチンがやったことはこれだ。
マキャベリいわく「力によって強制された約束を守らないとしても責むべきことではない」・・・ここでいう力とは利害と言い換えたほうがいいだろう。利害関係で結ばれた約束の無力さを知るばかりだ。
10時
餌を与えようとしている最中にまた猫が逃亡。ガスの検知機だか何だか知らんが、ふいの来客のおかげでオス4匹遁走してしまった・・・もうやってられん。
12時
最初に2匹何とか収容。あと2匹も捕獲、その収容時、入れ替わりにブサイクが遁走・・・やれやれ。てめえら国道でペッチャンコになりたいのか?!
【視聴予定】 21時
15-00 プロジェクトX「そして街中に音楽が飛び出した」 赤字工場逆転のカセットテープ戦争だ ---NHK総合テレビ
昭和44年、人類初の月面着陸に挑んだアポロ11号。その中に搭載された日本製品があった。ずば抜けた録音性能をもつ「日本製カセットテープ」だった。いつでも、どこでも、誰でも音楽が自由に楽しめる。音楽シーンを劇的に変え、全世界で年間20億本が売れた。根幹となる磁石の性質をもつ磁性素材の技術は、今も、IT社会を支えるフロッピーディスクやMO、ハードディスクドライブの磁気ヘッドに発展した。
この高性能カセットテープを開発。市場を制したのは、日本でも無名の電子部品メーカーだった。
敗戦後、製品の国産化に挑む日本の家電メーカー。それを一手に下支える部品会社があった。「東京電気化学工業(現・TDK)」。昭和10年、東京工業大学の研究者たちが、その研究成果を日本の産業に役立てて欲しいと技術を無償提供。会社は、受け継いだ磁性素材の技術で、テレビやラジオの根幹部分に使う電子部品を製造。日本家電業界隆盛の原動力となった。その会社の中、「お荷物部署」とやゆされる部門があった。テープ事業部。放送用オープンリールテープの国産化を果たすも、プロ用は数が出ず大きな利益にならない。一般市場は、あのソニーがレコーダーに加えテープまでも自社開発。セット販売していたため、付け入るすきが無かった。テープ事業部は在庫の山を抱え、巨額の赤字を抱えていた。
昭和37年、そこに転機が訪れる。テープ開発技術者の伊藤福蔵が、ヨーロッパのフィリップス社が考案した「カセットテープレコーダー」の試作品を入手。事業部は、赤字打破のため、いち早くそのテープの量産化に動き出した。間もなく、世界各国の家電メーカーがカセットテープレコーダーの販売を開始。プロジェクトのテープは、世界に先駆け量産化されたカセットテープとして販売された。
しかし、一年後。自体は一変する。アメリカの企業が後を追って大量生産を開始。一方、日本市場は破竹の勢いで伸びていたメーカー・ソニーが、自社開発のレコーダーとテープをセットで売り瞬く間に市場を席巻した。
その時、テープ事業部の総責任者・大歳寛、若き日、ちょ突猛進の営業マンと渾名された男がとんでもないことを言った。「俺たちの技術で世界をあっと言わせる新たなカセットテープが出来ないか。テープはレコーダーの付属品ではない」。部品メーカーが持つ下請け意識の脱却だった。その言葉に、伊藤等メンバーは、世界初高性能音楽用カセットテープ開発に打って出る。
番組は、部品メーカー・TDKが、技術力の総てを懸け世界初の音楽カセットテープを開発。巨大市場を自ら切り開き、誰もが知るトップメーカーにまでのし上がっていった苦闘のドラマを描く。
♀ 「新じねん」TOP
♂