|
|
|
★海賊、日本人船長ら3人拉致 マラッカ海峡
2005年03月15日01時46分
海賊行為の監視機関、国際海事局の海賊情報センター(クアラルンプール)によると、14日午後6時(日本時間同日午後7時)すぎ、マレーシア沖のマラッカ海峡で日本のタグボートが海賊に襲われ、日本人船長ら3人が拉致された。マレーシア警察が現場に向かった。
日本政府関係者によると、襲われた船は、北九州市に本社がある「近藤海事」に所属する「韋駄天(いだてん)」とみられる。シンガポールからミャンマー(ビルマ)に向かう途中、マレーシアのペナン島付近で襲撃されたという。
近藤海事によると、拉致された日本人は2人で井上信男船長と黒田俊司機関長とみられる。フィリピン人3等機関士も一緒に連れ去られた。
同センターによると、海賊は3隻の漁船に乗り、銃撃しながら乗り込んできた。「韋駄天」には、拉致された3人のほかに11人が乗り込んでいたが、無事だった。
「韋駄天」は、建設用運搬船「クロシオ1」を引いて航行していた。この船には日本人やマレーシア人ら154人が乗り込んでいたが、けが人などはなかった。
日本政府関係者によると、3人はインドネシア方面に連れ去られた。犯人側からの要求は同日夜時点ではないという。
韋駄天は事件後、ペナン島に向かって航行している。
日本政府は外務省と在マレーシア日本大使館に対策本部を設けた。マレーシア、シンガポール、インドネシアの3カ国に情報提供を依頼し、早期解放をめざす。
同海峡では12日夜にも、インドネシアの船会社所有のタンカーが機関銃などで武装した海賊に襲われ、船長と機関長が拉致された。船は解放されたが、身代金を要求されているという。拉致と身代金要求は、この海域の海賊の典型的な手口だ。
日本人船員が海賊被害に遭うのは、99年10月にインドネシア沖で起きた「レインボー事件」以来とみられる。この事件では貨物船アロンドラ・レインボーが襲われ、日本人2人を含む乗組員17人が6日間監禁された。その後、救命ボートで11日間、海上を漂流、タイの漁船に救出された。
マラッカ海峡ではスマトラ沖大地震とインド洋津波の前、海賊事件が増える傾向にあった。津波後約2カ月間、事件の発生はなかったが、2月28日に襲撃事件が発生し、船の乗組員が拉致されるなどしたため、同センターは警戒を呼びかけていた。
海賊情報センターは、国際商業会議所の国際海事局(在ロンドン)に属する民間機関。海賊事件の情報を収集して各国の捜査当局と連携するほか、人質解放交渉など事件の解決に尽力している。
★同僚、「祈る気持ち」 魔のマラッカ安否は
2005年03月15日02時28分
被害船を所有する海運会社は対策本部を設け、乗組員の安否を気遣った。魔の海峡で何があったのか。
15日午前1時すぎに近藤海事の事務所で記者会見した同社の石井秀夫専務(52)は拉致されたのは船長と機関長ら同社の3人と認めた上で、「犯人側からの要求や連絡は一切ない。乗組員が何とか助かってほしい、そのために全力を尽くしたい」と語った。
井上信男船長と黒田俊司機関長を乗せたタグボート・韋駄天(いだてん)が所属する北九州市若松区の近藤海事(近藤観司社長)。
関係者によると、近藤海事は新日鉄の下請けをしていたという。韋駄天が曳航(えいこう)していた貨物船「クロシオ」は、パイプラインを海底に敷設する工事船だったという。
|


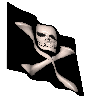
|
★【マラッカ海峡に海賊、日本人ら3人拉致】 マレーシア発10:20
2005.03.15(火)
NNA BUSINESS MAIL
http://nna.asia.ne.jp/
日本の外務省によると海賊が乗り込んだ小型漁船は、銃撃しながら「韋駄天」に接近。4〜5人が船内に乗り込み、船長らを銃で脅して連れ去ったとみられる。また、船長室、書庫などが荒らされ、金品や船舶関連書類が奪われた。「韋駄天」の船体には銃こん2発が残されていたという。事件当時、「韋駄天」には日本人8人、フィリピン人6人が乗り込んでいた。「韋駄天」は現在、無事だった乗組員11人を乗せ、ペナン島に向かっている。到着次第、ペナン総領事館が事件当時の状況について、乗組員から事情を聴く予定。
★「日本軍事情報センター」神浦元彰氏の見解
[コメント]タグボートはえい航したり、大型船を押す力を強めるために、スピードよりもけん引力を重視する性能となっている。さらに小型のために、漁船から乗りこみ易い船型である。そこを海賊に突かれれば、日本のタグボートは格好の獲物になる。大型石油タンカーのように放水などでは防ぎきれない。
それではハイテクを使った海賊対策として何が考えられるか。それは各船に緊急通信装置や、自船無線確認システム(IFF)を搭載することである。まずマラッカ海峡各地に無線通報監視施設を設置する。そして沖合を航行中の船舶に、無線で自動的に問いかけを行い、自動的に応答してもらうシステムを設置するのである。これで多くの船舶が常時、電子地図上に位置が記録される。
このような海のバッジシステム(日本の防空システム)を作るのである。その上で異常を通報した船、異様な動きを見せる船に対して、最寄りの飛行場から航空機で追跡を開始する。さらに高速警備船が海賊船を追跡する。もし追跡に必要なら、空から特殊ペンキなどの着色塗料弾を海賊船に投下して、警備艇の追跡を容易にする。
このようにマラッカ海峡に電子の網、航空機や警備船の追跡網、また海賊専門の特殊部隊の創設(多国籍部隊)を行う。そのようなマラッカ海峡での海賊対策が重要である。そしてその中心は日本の海上保安庁がリードすることが必要だ。まちがっても海賊対策に海軍を使っていけない。もし海賊対策に海軍が出れば、各地の海賊情報が集まらなくなるし、過剰に海賊を攻撃して事態を悪化させる危険があるからだ。
私なら海賊退治には海賊を使う。海賊を行って捕らえた者を、海賊退治の情報収集に投入するのである。そもそも海賊の元凶は貧困である。そして武器が大量に流れていることにも一因がある。そのような海賊の元凶を改善しつつ、海賊の情報を収集して先手を打つ。また海賊行為を行った者に関しては、徹底した追跡を行って壊滅させる。これが軍にはできない。
海のバッジシステムについては、もう20年も前に海上保安庁の人から船舶監視システムの説明(西太平洋を想定)を受けたことがある。海賊を「もぐら叩き」のように取り締まっても効果はない。
|
|
★東南アジア諸国の海賊対策
東南アジア諸国で沿岸警備隊など海上治安組織を創設する動きが活発化しています。海上輸送の大動脈であるマラッカ海峡を抱える東南アジアでは、海賊被害が後を絶たず、アメリカは海賊がテロ組織とつながりかねないとして、同海域での海上テロ対策を強化したい意向です。海上治安組織創設は、海軍が担う治安活動を海軍から分離することで、軍事協力のできなかった日本などの支援を得やすくして多国間協力を進め、アメリカの介入を避けたいとの思惑も背景にあります。
東南アジアの海上治安活動では、海軍と海上警察など複数の組織が混在し、海軍が主力です。1998年にフィリピンが海軍から分離して運輸通信省に沿岸警備隊を創設して以来、同様の傾向が加速し、海軍や警察など11の省庁にまたがっていたマレーシアでは今年(2005年)3月にも日本の海上保安庁をモデルにした「海上法令執行庁」を設立します。インドネシアも治安活動の統合化をめざす「海上治安調整機構」の設立準備を進めています。
いずれも日本が組織整備や人材育成の支援をおこなっており、現役とOBの海上保安官が派遣されています。先行したフィリピンの場合は、「海軍主体では日本のODA(政府開発援助)の対象にならず、財政難のなかで効率的な海上警備が出来ない。2国間、多国間協力が出来やすいよう沿岸警備隊を作った」(海軍高官)との打算的な考えがありました。
一方、日本は1999年に日本人が船長だった貨物船がマラッカ海峡で海賊に襲撃された事件を契機に、原油輸入の生命線であるシーレーンの安全確保のため地域協力の必要に迫られました。海上保安庁は2000年からインド沿岸警備隊と定期的な長官会談、巡視船の相互派遣をおこなっていますが、東南アジア諸国にも巡視船や航空機を派遣し連携訓練を重ねています。タイ元外相のスリン下院議員は「ASEANは海賊など国境を越える犯罪を地域安全保障問題ととらえていたが、地域的協力関係が組めなかった。日本のイニシアチブが多国間協力に向けたASEANの活性化につながっている」と語ります。
一方で、東南アジア諸国の間には、こうした地域協力によってアメリカ主導のテロ対策の介入圧力をけん制したいとの思惑も強くあります。マラッカ海峡でのタンカーや貨物船に対する海賊襲撃事件は、2002年16件だったのが2003年には28件、2004年上半期だけで20件の上ります。マラッカ海峡に接するインドネシア海域だけでも世界の海賊被害の4分の1に近い121件(2003年)おこっています。ファーゴ・アメリカ太平洋軍司令官は昨年3月、マラッカ海峡の海賊・テロ対策を目的に「地域海洋安全保障構想」(RMSI)を提唱しましたが、マレーシア、インドネシアが反発、両国海軍はインド海軍との合同パトロールの協議をおこなう一方、ASEANも昨年6月、中国と専門家フォーラムをシンガポールで開催、マラッカ海峡の安全対策を話し合い、アメリカのRMSIを阻んでいます。
マレーシア、インドネシアの海上治安組織創設も、多国間協力を導入し効率的な組織であることをアピールしてアメリカの批判を抑え込む狙いがあります。インドネシア政府のシンクタンク、戦略国際問題研究所は「ASEANは日本など域外国との協力を通じて、アメリカの地域プレゼンスを強化させないという原則を固めていくだろう。今は日本とASEANは人材育成を通じた協力関係だが、次の段階でどのような協力が出来るかについて地域安全保障にまで広げた議論が必要になる」と指摘します。
|
|
★海賊問題の現状と我が国の取り組み --外務省
平成13年12月
1.海賊事件の発生状況
(国際海事局(IMB)地域海賊報告センター年次報告書(2001年1月版)、国土交通省外航課調査より)
(1) 近年海賊事件は激増(カッコ内は、日本関係船舶の被害件数):
1995年188件(8件)、1999年300件(39件)、2000年は469件(31件)であった。
(2) 東南アジア及び南西アジアで多発:
2000年において、東南アジア及び南西アジアにおける海賊発生件数は305件(全体の約65%)となっており、海賊最多発地域である。具体的には、インドネシア119件、マレイシア21件、マラッカ海峡75件、バングラデシュ55件、インド35件である。
(3) 海賊の武装化・組織化:
銃やナイフで武装した海賊は増加(1999年139件、2000年183件)。船舶自体を奪取して売りさばく船舶のハイジャック事件は減少している(1999年10件、2000年6件)が、個々の船舶のハイジャック事件は、より組織化・凶悪化している。
(4) 日本関係船舶の主要事件:
(イ) 1998年9月:テンユウ号事件−インドネシア・スマトラ島クアラ・タンジュン港を韓国・仁川に向けて出港後、行方不明に。船体は、中国江蘇省張家港で発見されたが、乗組員及び積荷(アルミニウム塊約3,000トン)は依然行方不明のまま。
(ロ) 1999年10月:アロンドラ・レインボー号事件−インドネシア・スマトラ島クアラ・タンジュン港を日本・三池港に向け出港後、襲撃された。日本人の船長及び機関長を含む乗組員全員は漂流中にタイで無事保護。船体はインド西方でインド海軍により捕捉。積荷(アルミニウム塊約7,000トン)の一部はマニラで発見された。
(ハ) 2000年2月:グローバル・マース号事件−マレイシア・ポートケラン港をインド・ハルディアに向けて出港後、タイのプーケット沖において襲撃された。乗組員全員はタイで無事保護。船体は中国広東省珠海にて中国公安当局により発見・捕捉
|
|

3−11℃

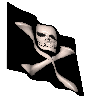
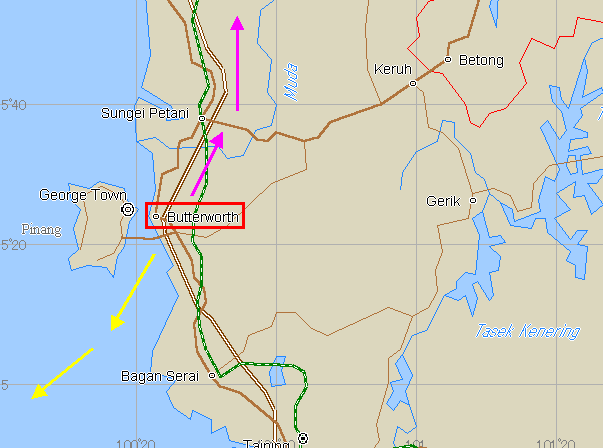
「新じねん」TOP
♂