●4名の死亡について、責任を認めない関電
「4人の死亡は申し訳ないが、関電に責任があるかは言えない」(関電)
美浜3号事故についての交渉冒頭で、「4名の作業員の方々が亡くなられ、多くの方を負傷させたことについて、責任を認めるか」と関電の責任を質した。これに対して関電は、破断の原因に関係する説明を長々と続け、責任に触れようとしなかった。会場から怒りの声がわき上がり、「それでは藤社長は土下座して何を謝っているのか」と追及すると、「関電の建物の中でこういうことが起こったということが申し訳ないのだ」と答えた。何度訊いても「原因を究明中であり、責任云々については言えない」と繰り返し、決して「責任がある」とは認めない。
しかし、「原発の所有者は関電であり、その管理責任は関電にあるのではないのか」と追及すると、「確かに管理責任は当社にある」とは認めた。そこで「原発の管理責任がありながら、28年間も検査せず、安全に管理・運転してこなかった関電に責任があるのは当然ではないのか」と追及すると、関電は答えに窮し、黙り込んでしまった。結局、最後まで「責任がある」とは認めなかった。
このような姿勢を関電がとるのは、刑法上の責任が追及されるのを恐れるためであろう。結局、藤社長の土下座は、責任を認めないための単なるポーズに過ぎないのである。
「他の原発を止める必要なし」「高浜1号では、96年の検査で安全を確認しているから」(関電)
【詳細】 美浜の会より
★原発事故発生シュミレーション-第5部 無延性遷移温度(NDT)について
○○電力○○原発2号機の圧力容器内に置かれていたその試験片のNDTは、製造時のマイナス18度Cから、運転開始後1年2カ月の第1回試験でプラス4度Cに、第2回の5年9カ月後の試験では実に80度も高いプラス52度Cにまで上昇していた。当初は酷寒の環境下でも強靭な延性を持っていたはずの圧力容器材料の鋼が、常温どころか熱湯の中でさえも脆性破壊を起こしうる「もろい」鋼へと劣化していたのである。
通常、運転中の圧力容器の温度は300度にも達するのだから脆性破壊を起こすような温度条件が運転中に満たされることはまずない。
だが、運転中には157気圧に加圧された一次冷却水のせいで圧力容器を凄まじい力で破壊しようとする力が常にかかっていることを忘れるわけにはいかない。また、例えば緊急炉心冷却装置(ECCS)が作動して急激に炉心に高圧常温の冷却水が押し込まれたなら、圧力の急変に加えて温度の急変によるショックが加わることになる。
圧力の変化もさることながら、NDTの下がった、つまりそれだけ延性を失ってもろくなった圧力容器に温度の急変が与える影響は重大である。急激な温度変化が起きると構造物の内部に温度分布の大幅な傾斜を生じ、その膨張の違いが材料内部に大きな引っ張り応力を発生させることが原因で「加圧熱衝撃(PTS)」と呼ばれる危険きわまりない現象が起きる。
しかもECCS作動によって流入した冷水は肉の厚い圧力容器壁内側と外側の間に大きな温度差を生みだし、圧力容器には水圧のみならずこの温度差による引っ張り応力が衝撃的に加算されて働く。これがPTSだ。小さなクラックが引き金となって圧力容器の脆性破壊が一気に進行する事態も予想されるのだ。
【詳細】
美浜2号機は1991年のSG細管破断事故で既にECCS起動を経験しており、圧力容器の脆性遷移温度はさらに危険なレベルにまで上昇しているものと考えられる。
もし加圧熱衝撃による原子炉圧力容器の破壊が起きれば、ブローダウンにより一挙に冷却水が失われ炉心がむき出しになって炉心溶融事故へと進む恐れがある。これは、「ブローダウン→炉心温度上昇→燃料被覆管と水の発熱反応→水素発生→炉心崩壊→燃料棒溶融→原子炉圧力容器底部へ落下→原子炉圧力容器溶融貫通」とたどる悪夢のシナリオであり、この中盤から後半のどこかで水素爆発または水蒸気爆発が起きてもおかしくない。
【詳細】
★延性−脆性遷移温度の上昇
体心立方晶(bcc)金属では、通常室温から低温になると衝撃荷重に対して著しく脆くなることが知られています。しかし、温度を上昇させていくとある温度で脆性(brittle)から延性(ductile)へ変化します。これを延性−脆性遷移温度(DBTT:ductile-brittle transition
temperature)といい、通常シャルピー衝撃試験によってこの遷移温度は確かめられます。
中性子照射を受けた金属材料は、この延性−脆性遷移温度が高温側に遷移することが知られています。遷移温度が室温付近まで上昇してくると、炉用構造材としては危ない状態にあると言えます。なぜなら、通常の商業用原子炉では核分裂の連鎖反応が予期しない事態によって制御不能になった場合、炉が過熱状態になると緊急冷却を行うためにECCS(Emergency Core Cooling System)と呼ばれる強制冷却水注入装置が備え付けられています。日本にある原子力発電所で使用されている原子炉は、主に加圧水型(PWR:Pressurized Water Reactor)と沸騰水型(BWR:Boiling Water Reactor)の二つのタイプに分かれますが、運転時の炉内の温度は加圧水型で290〜330℃、沸騰水型で280〜290℃になります。実際に原子炉が制御不能になってECCSが働いたとした場合、炉内の温度は急激に室温付近まで冷やされるため熱応力が発生します。その際に、延性−脆性遷移温度が室温付近まで上昇していた場合、圧力容器鋼に破損が生じ、内部の放射性物質が外に漏れる可能性が出てきます。このため、原子炉がある一定期間運転が行われた後には、予め炉内に用意しておいた試験片を取りだして衝撃試験を行い、構造材の照射脆化が危険な状態に達していないか定期的な検査が行われています。
【詳細】
【私的めもらんだむ】
▼7時
原子炉建屋とタービン建屋の設計図を見つけた。アメリカ原発のものだが、美浜原発1号機がアメリカ製だからほぼ構造は同じと思って間違いはないだろう。これを3DCGで作りたい。ちと手間がかかるだろうなぁ。美浜原発事故の現場写真もニュースで流れている。それらも参考にしたい。それと上記のように、いま脆性遷移温度について調べているが、今度の事故は水蒸気噴出よりも深刻な事態だったことを知って興奮している。
それに加えて、小猫たちが仏壇をメチャクチャにしてくれた。妹が見たら卒倒しかねない荒れようだ。早く片付けねば・・・猫に振り回される人生、前世の祟りか?でも、小猫って可愛いんだよね。癇癪を起こしつつも憎めない。やれやれ・・・
▼12時、室内気温30℃、湿度55%
美浜原発事故を再検証してみる。8月9日、午後3時28分にタービン異常警報が出て原子炉とタービンが自動停止したということは、緊急炉心冷却装置(ECCS)が作動したということになるのだろう。このとき蒸気発生器の2次側に減圧沸騰が生じ、1次側から熱を奪いながら圧力容器は急速に冷却される。そうすると脆性遷移温度(ぜいせいせんいおんど)以下に急冷されてしまいかねない危険が出てくる。原子炉内が室内温度まで急速に下がっていく過程で、熱応力による圧力容器の破損を招きかねないのだ。まさしく上記「原発事故発生シュミレーション」のように・・・
「急激な温度変化が起きると構造物の内部に温度分布の大幅な傾斜を生じ、その膨張の違いが材料内部に大きな引っ張り応力を発生させることが原因で「加圧熱衝撃(PTS)」と呼ばれる危険きわまりない現象が起きる。しかもECCS作動によって流入した冷水は肉の厚い圧力容器壁内側と外側の間に大きな温度差を生みだし、圧力容器には水圧のみならずこの温度差による引っ張り応力が衝撃的に加算されて働く。これがPTSだ。小さなクラックが引き金となって圧力容器の脆性破壊が一気に進行する事態も予想されるのだ」・・・ということになる。
つまり簡単に云ってしまえば、美浜原発の水蒸気噴出事故は「2次側の水蒸気が大量に噴出したことによって1次系の急冷を招き、そのために圧力容器の肉厚温度差で脆性破壊する恐れがあった」ということになろうか。これまでの動きをみると、電力側は問題の核心を水蒸気噴出の直接的原因であるところの「延性割れ」だけに留めておきたいようだ。だから水蒸気が噴出したのだと、それが同時に「圧力容器の破壊」を招きかねない異常事態だったことは口を裂けても云えない。事故勃発直後から執拗に「放射能漏れはない」と繰り返したのも納得がいくというものだ。同じようなトラブルを抱える原発を「止める必要なし」として、事故の「責任があるかは言えない」とする関西電力には開いた口が塞がらぬ。
私の頭も沸騰しそう、キンキンに冷えたビールで冷却しなければ爆発してしまうぞ!・・・なわけ、ないか。
▼14時
配管破断の直接的原因となった流量測定計「オリフィス」部位について調べた。すると平成13年5月に核燃料サイクル機構が「新型転換炉ふげん発電所の原子炉手動停止について」と題するオリフィスに関しての記述があった。
★新型転換炉ふげん発電所の原子炉手動停止について
(ヘリウム循環系配管からのトリチウム漏えいの原因と対策)
新型転換炉ふげん発電所(新型転換炉;定格出力16.5万kW)は、平成13年1月19日から本格運転中でしたが、1月下旬以降、主排気筒トリチウム濃度の分析値が通常値より高い傾向を示していたことから、4月中旬からトリチウム放出源の調査を行いました。
この結果、アニュラス(原子炉格納容器と外周コンクリート壁の間の密封空間)内のヘリウム循環系配管からの漏えいと判断し、5月24日に原子炉を停止しました。
原子炉補助建屋内については、流量計オリフィス部より下流側では、ほぼ全ての配管溶接部近傍で指示が確認されましたが、オリフィス部より上流側のヘリウム冷却器までの配管では指示が数箇所でした。
※オリフィス:管路の途中に挿入して流路を絞り、変化した圧力を検出して流量を測定するための穴のあいた円盤。
オリフィス部下流側の8インチ配管内面には、水が溜まっていた跡のような変色が確認されるとともに、原子炉格納容器内までの配管内面に斑点状の変色が見られました。割れは内面を起点とした粒内応力腐食割れで、オリフィス部下流側での割れの深さは、配管厚さ(6mm)の1/2程度まで進展したものも見られました。オリフィス部下流側の8インチ配管内に塩素濃度の高い重水が溜まった状態が試運転開始当初から継続していました。重水が溜まった配管内をヘリウムが高速で流れることにより、重水の飛沫が下流側配管内に運ばれ、配管内面で付着・乾燥し、塩素が濃縮する現象が継続的に生じており、残留応力の高い溶接部近傍で内面から塩素による粒内応力腐食割れが発生したものと推定されました。
【詳細】
★オリフィス流量計
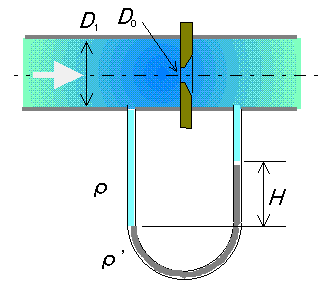
管内を流れる流体はこの円孔を通過するさい、流路の断面積が縮小して流速が増大し、下流での静圧が低下する。この静圧低下は流量にほぼ比例するから、オリフィス板前後の圧力差(差圧)を測定することで流量を知ることができる。このオリフィス計による流量測定はJISなどによりオリフィス板の形状、測定法などが標準化されている。
【詳細】
ヘリウム循環系配管とタービンからの復水配管との違いを除けば、ふげん発電所の原子炉手動停止と、今回の美浜原発事故のオリフィス部位のトラブルは酷似する。図を見て驚かされるのは、その水蒸気が通過する円孔口径の小さいことだ。現場写真を見ると、確かにオリフィス部位は配管の肉厚が厚くなっている。しかし、それもオリフィス部位に限ってのことで幅20センチに満たないリング状のもののようだ。白く色分けされているのですぐに確認できる。破損箇所はそのリングの手前で起きている。高温の水蒸気が円盤状のオリフィスの穴に猛スピードで突進して還流が起き、ために1センチの肉厚しかない復水配管内部が磨耗しつづけ、ついには破断したということになる。原子力エネルギーの規模からいって、それは想像を越える勢いで、一瞬にして10メートル離れた人間を吹き飛ばしたのだ。ふげん原子炉停止事故において気になるのは、この時点でオリフィス付近の配管肉厚が半分に磨耗していたという調査報告が成されていたことだ。当然ながら関西電力もその報告を受けていたはずだ。結果的に、それらが何の教訓ともならず、今回のような4人もの死者を出した事故に繋がってしまったことは、やはり電力会社にも責任追求があってしかるべきだろう。
【視聴予定】
21時
00-58 NHKスペシャル「一兵卒の戦争」 作家・古山高麗雄が問い続けた戦争▽中国・雲南戦線の記録▽元兵士の証言 -NHK総合テレビ
六十年前、中国・雲南省では日本軍と中国軍・米英軍との間で激烈な戦いが繰り広げられた。龍陵での戦いには、作家・古山高麗雄が一兵卒として送り込まれた。古山は戦後、自らの戦争体験を亡くなるまで書き続けた。戦争に生き残った古山がこだわり続けたものは何だったのか。一兵卒の感じた戦争を描いた著作とともに、古山と同じ部隊に所属した元兵士の証言を交えて、六十年前の戦争の記憶を伝える。
|

23〜32℃、北西〜南よりの微風
「新じねん」TOP
♂